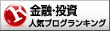GAFAがアクセス遮断されている中国において、BAT(baidu,Alibaba,Tencent)という代替企業が時価総額を急激に高めています。
BATの中でも世界時価総額ランキング上位に名を連ねているアリババですが
「名前は聞くけども、何やっている会社?中国のアマゾン?」
「どれくらい成長している企業なの?」
「どのような戦略をもっているの?」
と、言った疑問があるかと思います。
この記事では阿里巴巴(アリババ Alibaba)という企業について
・アリババグループの略的、どのように成長してきたか
・ソフトバンクグループとの関係
・収益源の事業と今後の展望
を中心に解説したいと思います。
Contents
阿里巴巴グループの略歴

1999年3月に創業し、BtoB電子商取引を中心と開業されました。
アリババのサクセスストーリーは創業者であるジャック・マーのドキュメンタリーとして映画化もされていたりもします。
https://www.youtube.com/watch?v=RkVJNOQ7B74&feature=youtu.be
英語教師をしていたジャック・マーはアパートの1室で17人の仲間とスタートアップしました。
一室から始まったスタートアップは20年で従業員10万人、時価総額50兆円超の会社へと急成長します。
なぜECサイトを始めたか?
創業者ジャック・マーは海外で中国の会社の知名度が異常に低いことに気づきました。
例えばビールの会社であれば日本・ドイツの企業は出てくるものの、中国の会社は出てこないことに気づきました。
そこでインターネットを通じて中国の情報を発信することを思いつきます。
中国市場では支払いは遅ければ遅いほど美徳、と言われているほど債権回収が難しいです。
製品情報を載せ、大口購入の顧客が買い取るというECサイトの仕組みを手数料無料で打ち出します。
独身の日(11月11日)など大規模なセールを行う際、流通量と売上高が別で報道される仕組みはこのときの名残です。
阿里巴巴は競合を中国国内では無くシリコンバレーと見ていたようで、IPOまでの期間は996システム(朝9時から夜9時まで週6日)に代表されるように、多大な労働時間で働きました。
アリババ成長への基本戦略は安さ

amazonの経営理念に「顧客中心主義」というものがあり、安さを喜ばない客はいない、というものがあります。
阿里巴巴でも同様の理念があり安さ=手数料無料を武器に戦いを仕掛けて行きます。
アリババのプラットフォームは徹底的に会員を増やすことに注力しており無料戦略を貫いていきます。
例を挙げると
取引間の手数料収入では無く、有料会員の会費を収益とするBtoBプラットフォーム
大量購入者間を結びつけるBtoBプラットフォームを手数料無料で開始します。
一部の有料会員で収益を得るものの、基本的にはこの時点では赤字。
PayPal資本のCtoCプラットフォームeBayの参入時にも手数料無料を貫く
PayPalは日本ではCtoCオークションサービスとして参入するもYahooに負け撤退しており中国へは1億ドルを超える投資を行いました。
PayPalの収益モデルはCtoC取引間で手数料を取る収益モデルでしたが
阿里巴巴はCtoC(タオバオワン)にも無料戦略を取り、ユーザー数を拡大させました。
PayPalに対抗して電子決済サービスを開始。これももちろん無料
PayPalの収入源を潰すため、電子決済サービス「アリペイ」を導入。タオバオワンでの手数料を無料にしました。結果eBayは収益を取れず中国市場から撤退します。
無料サービスから手数料サービスへの移行
手数料無料を貫いてきたアリババでユーザー数は増えたものの、このままでは収益性がありません。
そこで天猫というBtoCサービスを開始しeコマース事業へ参入します。
ここでアリペイによる手数料とBtoC出店手数料をとることで収益化に成功し、中国という巨大マーケットを手中に収めることに成功します。
ソフトバンクとの関係

2000年に2000万ドル(20億円)、2004年に6000万ドルの融資をソフトバンクより受けています。現在の主要株主はソフトバンク29.2% ヤフー15%となっています。現在の時価総額は4970億ドル(50兆円)となっていますので概ね1000倍近くの暴騰となっています。
当時は無名であった中国企業に対し、融資を実行する目を持っていることが非常に優れていると感じますね。孫さんが投資を決めた最終判断は眼だったそうです。野獣の匂いを感じた。とのこと。
阿里巴巴グループの売上高推移(単位:元)

次に売上の推移を見ていきます。
指数的に伸びていることが眼に取れます。2018年の売上高は376,844百万人民元(5兆6千億円 前年比50%増)となっています。純利益は87,600百万人民元(1兆3千億円)利益率は23%となっています。

次に売上の割合を見ていきます。
8割強をECサイトで稼いでいます。ただし投資に伴い、粗利率は減少しています。

阿里巴巴グループの事業

上記でも少し説明しましたがコア事業として
・CtoCプラットフォーム 淘宝網タオパオ 日本で言うところのヤフオク
・Amazon転売ヤーにはおなじみの アリエクスプレス 日本で言うところのAmazon
・BtoBプラットフォーム 1688.com アリエクよりも比較的安価、大ロット
・広告プラットフォーム 阿里妈妈(アリママ) 日本で言うところのGoogleアドセンス
・物流 ツァイニャオ
・クラウド Alibabaクラウド(中国シェア50%)
・QR決済 アリペイ
と、Eコマースに関わる事業を抑えています。

中国シェア50%を超えるAlibabaクラウドの展望
8月にテンセントが日本でのクラウド事業に参加することを発表しました。
日本では圧倒的にAmazon(AWS)、次いでGoogle(GCP)、Microsoft(Azure)と続きます。
中国内ではGoogle、Amazonを遮断する国策検閲ファイアーウォール(通称 金盾)の影響もあり、圧倒的に中国企業がシェアを取っています。
アジア向けでシェアを取るため、中国国内法の検閲を回避する必要があり、リージョンごとに拠点を分散しています。
例えば日本国内では、日本リージョンにデータを保管しており中国当局のデータ提出要請を回避しています。(ただし、中国共産党をどこまで信じられるか、が重要な気もしますが)

まとめ
今回の記事をまとめると
・中国内では徹底的に無料戦略を貫き、ユーザー数を増やすことに注力
・競合がいなくなったところで、ECにかかわる事業をすべて抑える
・次の事業はECからクラウドへ。
と、なります。
以上で、ざっくりと阿里巴巴について調べてみました。
中国国内でのシェアを取る経緯など、個人的には面白いと思います。
中国市場は地球規模で見て20%に届こうとしている巨大マーケットです。
正直国策企業として、楽をしてマーケットを取っている印象がありましたがやはり企業成長には明確なビジョン、そして多大な努力、運が必要なのだと改めて感じました。
中国版GAFAとしてバイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイの頭文字を取ったBATH、というものがあります。
テンセントについてはこちらにまとめましたのでご覧ください
筆者は阿里巴巴の成長を応援致します。